ジャンピュータ時代のアーケード麻雀。
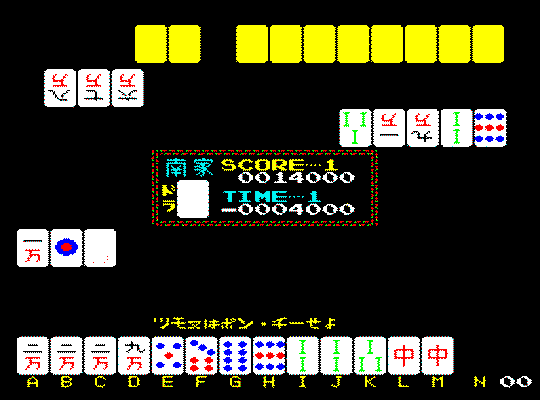
アーケード向けコンピュータ麻雀の元祖と言えるジャンピュータ(アルファ電子・三立技研)がリリースされた昭和56年(西暦1981年)頃のアーケード麻雀事情について。
ジャンピュータの流れを汲まなかった作品。
昭和56年(西暦1981年)にジャンピュータがアルファ電子に依って開発された結果、ゲームセンタやゲーム喫茶にはコンピュータ麻雀が多数置かれる事となりました。
その殆どはジャンピュータかそれを基とした作品でしたが、流れを汲まなかった作品も僅かとは言えありました。
DSテレジャン(データイースト)。
- 詳細はDSテレジャン(データイースト)のお話しを御覧ください。
DSテレジャンは、データイースト社に依って開発された、ジャンピュータの流れを汲まない初のアーケード麻雀でした。
当時データイーストは、デコカセットシステムと呼ばれる共通基盤を開発しており、DSテレジャンもこのシステム上で動作する作品でした。
この製品のプロトタイプは、麻雀用具メーカーだったかきぬま社と共同開発したテレジャンでした。
テレジャンはアーケードゲーム筐体と言うより、全自動麻雀卓の進化形として開発されました。
コンピュータに思考ルーティンを搭載せず、必ず四人が集まらないとプレイ出来ないものだったのです。
四人の手牌は衝立で隠され、互いに見る事が出来ないようになっておりました。
テレジャンは全くと言って良い程成功しませんでしたが、テレジャンにヒントを得たデータイースト社は、これをベースにアーケード版のDSテレジャンを開発したと言う訳です。
DSテレジャンの売りは、
- デコカセットシステムで提供されるので、当該システムを既に導入しているところであれば、専用キーボード, 専用衝立と磁気テープを買うだけで導入出来る事
- ジャンピュータのような対コンピュータプレイのみならず、二人での対局も可能になっている事
が挙げられました。
DSテレジャンはジャンピュータのデッドコピーなんかでは決してありませんでした。
- 技術的な観点で言えば、CPUが全く違うため、コードの流用などあり得ませんでした。ちなみにデコカセットシステムのCPUはMOS6502、ジャンピュータのそれはZ80でした。
デコカセットシステムでの提供である事もあって、ジャンピュータほどではないものの、そこそこ普及しておりました。
また、DSテレジャンにヒントを得たのか、日本物産やタイトーもジャンピュータベースの対局対応麻雀をリリースしました。
ロンⅡ(サンリツ電気)。
ジャンピュータのリリースから遅れた昭和57年(西暦1982年)、サンリツ電気もアーケード麻雀をリリースしました。
- ジャンピュータはサンリツ電気の作品と誤解している方も多いようですが、ジャンピュータは三立技研(東京都新宿区)の販売であり、サンリツ電気(相模原市中央区)は一切関与しておりません。
既に様々なものが出ていた事もあり、それらを一通り実装したのがロンでしたが、こちらは余り普及せず、その後出された改良版のロンⅡで、漸くそれなりの売上げを得るようになりました。
ロンⅡは、当時のアーケード麻雀の中では、最も本格的な仕様になっておりました。
- 二人対局可能
- 槓ドラ・槓裏ドラ実装
- 積み棒・不聴罰実装
- 九種九牌・オープン立直(二人対局時のみ)実装
このリリースののち、初の本格四人打ち麻雀としてリリースされたのが、四人打ち麻雀ジャントツでした。
ロンⅡは、ジャンピュータと同じZ80をCPUにしていたようですが、ジャンピュータとは全くの別物でした。
ジャンピュータの流れを汲む主な作品。
ジャンピュータの流れを汲む作品は数え切れない程ありました。
その中で個人的に特筆すべきと思われるものを挙げておきます。
対局コンピュータマージャン(日本物産)。
データイースト社のDSテレジャンにヒントを得たと思われる製品でした。
日本物産は、三立技研から正規に許諾を受けてコンピュータマージャンをリリースしておりましたが、実際のところ殆ど市場に出廻っていなかったのが実情でした。
- 日本物産はクレイジークライマーやムーンクレスタのようなヒット作を出し続けていたにも拘らず、コンピュータマージャンは余り普及しなかったのです。
- 尚、ジャンピュータとせずにコンピュータマージャンとしたのは、第三社がジャンピュータの商標権を持っている事が明らかになったからだそうです。
その後、対局機能を実装した対局コンピュータマージャンがリリースされ、こちらはそこそこ市場に出廻るようになりました。
対局コンピュータマージャンは基本的にジャンピュータと同じですが、二人の手牌を衝立で隠す事で、対局を可能にしておりました。
また、オリジナルのジャンピュータにはプレイ中に反対側のキーボードを弄られるとこちら側の操作が出来なくなると言う不具合があったのですが、反対側のキーボードが常に触られる筈である対局を考慮してこの問題を改善しておりました。
ところが、この対局コンピュータマージャン、皮肉な事にオリジナルよりもデッドコピー品の方がより大量に市場に出廻ってしまったのです。
デッドコピー品に見られた特徴として、相手の操作中に摸牌ボタンを一回でも押すと、相手の打牌後に直ちに摸牌すると言う不具合がありました。
- この不具合は日本物産のクレジットが入ったオリジナル版では一切見られませんでした。逆に、ニチブツのクレジットのないデッドコピー品では必ず見られました。
勿論、一切チー・ポンなどをするつもりがない場合には、この機能を利用する事で、摸牌時のタイマ減少を避ける事が出来るのですが、チー・ポンを考えている場合には、チー・ポンしたくても出来ずに勝手に摸牌されてしまう事になります。
TTマージャン2(タイトー)。
こちらもデータイースト社のDSテレジャンにヒントを得たと思われる製品でした。
タイトーも、三立技研から正規に許諾を受けてTTマージャンをリリースしておりましたが、タイトーの直営店やフランチャイズ店でしか見られなかったのが実情でした。
- タイトーの場合、直営店やフランチャイズ店で稼動する筐体には、独自のタッチのキーボードを搭載して販売しておりました。
- 尚、ジャンピュータとせずにTTマージャンとしたのは、これも日本物産同様商標権問題が絡んでいたからだそうです。
その後、対局機能を実装したTTマージャン2がリリースされましたが、やはりこちらもタイトー直営店及びフランチャイズ店でのみの展開でした。
TTマージャン2は基本的にジャンピュータと同じですが、二人の手牌を衝立で隠す事で、対局を可能にしておりました。
また、槓でドラが増える機能も追加され、より本格的になりました。
加えて、日本物産の対局コンピュータマージャン同様、オリジナルのジャンピュータに見られたキーボードの不具合を解消しておりました。
ジャンピュータの流れを汲んだアーケード麻雀の中では、最も本格的なものだったにも拘らず、タイトーの直営店やフランチャイズ店でしか見られなかったもので、デッドコピー品すら市場に出廻る事はありませんでした。